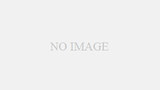私の住む豊島(とよしま)と同じ字を書くけど全く違う東京都豊島区(としま)で活躍されている、青木純さんのお話を聞きました。
私も東京時代巣鴨に住んでいたこともあるし、池袋もたくさん行っていたので馴染みのある場所。その場所がどう変わっていったのかというお話は大変興味深かったです。

巣鴨のまち1 
巣鴨のまち2 
巣鴨のまち3
何度も、「豊島区だからできたんでしょ」「でも豊島区だから起こった問題もあります」を繰り返される。たしかに、彼の成功体験を呉で話すと。そして、私の頭の中には島でそれをやろうとしている自分がいる。どこがリンクする部分で、自分の事業で学べるところはどこか。それを探しながら聞いていました。そのリンクする部分をいくつかまとめてみたいと思います。
「顔の見える関係」を作れば、よい関係ができる。
青木さんは大家さんの本業として、住民同士を顔の見える関係にすることで良いことがたくさん起こったそうです。確かに、私も賃借人として20年で10件弱の物件に住んできたけど、建物のことは覚えていても大家さんの顔や隣の人の顔とか全然覚えていない。多分見たこともないのがほとんどのはず。。そのような状態だと、大家にとって賃借人はトラブルのもとという認識になっていくんだとか。(家賃滞納や公共の場の騒音、汚したりetc…)

昔住んでいた家1 
昔住んでいた家2 
昔住んでいた家3
入居者同士も知り合いをもつ、DIYしてもらうことで、その部屋に愛着を持ってもらう。そのことで長く住んでもらえるし、入りたい人と直接あって話す、大家側のヒトトナリや物件を運営している経緯、も知ってもらうことが大事。シェアハウスなんかなら当たり前なんだろうけど、これは今後、住んで貰う人を探す際には本当に肝に銘じてやりたいなって思いました。
共感を連鎖させる
模倣できるような例を示すことで、事例に共感し、次にリスクを取る人が増えてくる。そのうちの一つが、後継に前例を示すこと。警察や行政に禁止されていたことを説得してやりきった実績を少しずつ積み上げていくこと。たとえば、歩道にベンチを置く、といった一つでも、道路の占有ということで警察マターになってくる。
これを実現させることでコミュニケーションが生まれる。インバウンドの方々は、自分の国では当たり前なのでこういう景色になれているそうだ。ここに英語で観光案内できます!とか書いておくと、会話の実地訓練にもなるなぁ。
コミュニケーションを諦めない。
チームとして、柔軟性を持って継続する。自分ではできないコミュニケーションも、他の人ならできるかも。特に、伝統的に仲が悪い集落同士のコミュニケーションはどこかで、やらなければいけないこと。自分だとしんどいけど、誰だったらできるか?(丸投げしないように気をつけながら)考えてみたい。
初めて呉の屋台にも。